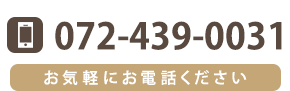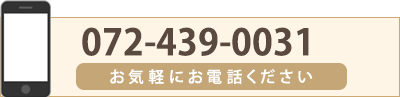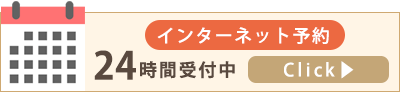ワクチンの接種スケジュール
- ワクチンの接種スケジュール
- 五種混合ワクチンの接種スケジュール
- 同時接種について
- ワクチンの種類
- ワクチンの料金
- 小児のインフルエンザワクチンの接種回数
- ロタウイルスワクチンについて
- 子宮頚がんを防ぐワクチンについて
- おたふくかぜについて
- ワクチンの副作用について

入口を「お客様入口」と「患者様入口」に分けて、健康なお子様が患者様から病気をうつされないように、患者様のいない場所で、ワクチン接種ができる「予防接種所」を設けました。

予防接種スペースは「待合室」と「予防接種スペース」に分けています。
あぶみ小児科クリニックで任意接種を受けている割合は、おたふくかぜ 96% (MR1期+2期の接種数との比較)です。
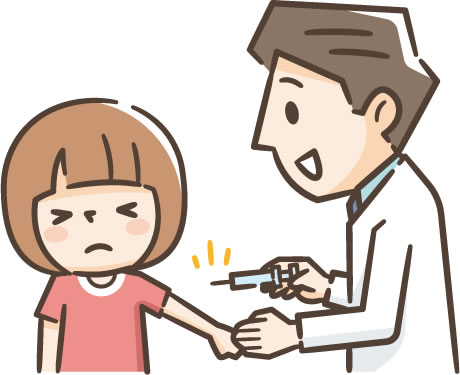
小さいうちにかかればかかるほど病気は重くなるものなので、本来ワクチンは、受けられる年齢に達したら、なるべく早く受けるべきものです!
| 2カ月 | 五種混合(DPT・IPV・Hib)(1)+肺炎球菌(1)+B型肝炎(1)+ロタウイルス(1) |
| 3カ月 | 五種混合(DPT・IPV・Hib)(2)+肺炎球菌(2)+B型肝炎(2)+ロタウイルス(2) |
| 4カ月 | Hib(3)+肺炎球菌(3)+ロタウイルス(3) |
| 5カ月 | BCG |
| 8カ月 | B型肝炎(2) |
| 10カ月 | 五種混合(DPT・IPV・Hib)(3)+乳児後期健診 |
| 11カ月 | Hib(4) |
| 1歳 | 麻疹風疹混合(MR)(1)+おたふくかぜ(1)+水ぼうそう(1)+肺炎球菌(4) |
| 1歳3カ月 | 水ぼうそう(2) |
| 3歳 | 日本脳炎(1) |
| 4週後に | 日本脳炎(2) |
| 4歳 | 日本脳炎(3) |
| 5歳~6歳 | 五種混合(DPT・IPV・Hib)(4)+おたふくかぜ(2) |
| 就学前の1年間 | 麻疹風疹混合(MR)(2) |
| 小学4年 | 日本脳炎(4) |
| 小学6年 | 二種混合(DT) |
| 小学6年~高校1年の女子 | 子宮頚がんワクチン計3回 |
「ヒブ」と「肺炎球菌」は、2カ月から5歳未満
「子宮頚がんワクチン」は、小学6年から高校1年までの女子生徒
が、費用補助の対象者なので、対象年齢の人は早めに受けられるのがいいです。
生まれたばかりで、これからワクチンを始める赤ちゃんなら、きちんと接種スケジュールを立てて重要なワクチンから優先して受けていくべきでしょう。
お母さんからもらった移行免役は、生後2カ月からが減り始め、生後6カ月にゼロになります。
赤ちゃんのうちは病気にかかりにくいというのも6か月までの話です。
つまり、0才のうちに受けるワクチンは6か月までに済ませるべきなのです。
1才を過ぎれば受けられる生ワクチンも、1才を過ぎればなるべく早く受けるべきです。
生後2カ月で、五種混合とヒブと肺炎球菌とロタウイルスとB型肝炎ワクチンを受け始めます。
5カ月でBCGを受けます。
ヒブと肺炎球菌、ロタウイルスワクチンはこの時期に3回あります。
B型肝炎は1回目から20週以降(6カ月後が推奨)で、五種混合は2回目から6カ月以降で、それぞれの3回目を済ませます。乳児後期健診はこの時期にあるので同時に済まされるのをお勧めします。
ヒブワクチンは3回目から7カ月以降で追加接種ができ、1才になったら、麻疹風疹混合(MR)とおたふくかぜ、水ぼうそうの1回目と肺炎球菌の追加接種を済ませます。
1回目の水ぼうそうから標準的には6カ月で保育園児は3か月で2回目の水ぼうそうを受けます。
生後2カ月から6カ月までと、1才過ぎが過密スケジュールです。
五種混合ワクチンの接種スケジュール
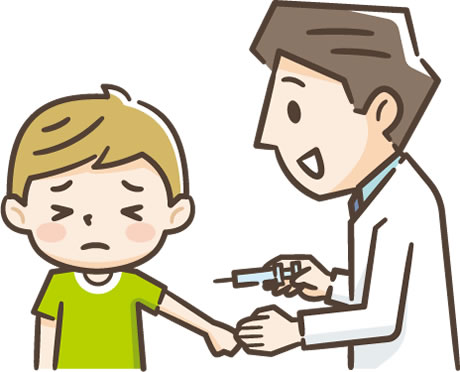
以前に実施されていた三種混合ワクチンの標準接種スケジュールは生後3か月から3~8週間隔で3回接種して、1年後に4回目を接種するものでした。
不活化ポリオワクチンの世界の標準接種スケジュールは、1回目と2回目の間を1カ月から2カ月、2回目と3回目の間は半年以上あけて、4回目は3回目から3年以上あけて4才以上で接種するものです。
平成25年9月に経口生ポリオワクチンから注射の不活化ポリオワクチンへ切り替わりましたが、不活化ポリオワクチンを単独で接種している間は、多くの小児科医はこの世界標準のスケジュールで接種していました。
平成25年11月に始まった三種混合ワクチンに不活化ポリオワクチンを混ぜた四種混合ワクチンの推奨される接種スケジュールは、従来の三種混合ワクチンと同じで、生後3か月から3~8週間隔で3回接種して、1年後に4回目を接種することになりました。
実は不活化ワクチンの効果の持続期間は短いので、五種混合ワクチンを採用している先進国では就学前に5回目を接種するのが一般的で、4歳以上で受けていないと接種を終了したとみなされません。しかし、日本では5回目の接種の予定がないので、現在の推奨スケジュール(従来の三種混合ワクチンと同じ)のままだと、小学校入学の頃にはポリオや百日咳の免疫が消えてしまいます。5回目を任意接種として受ける方法はありますが、定期接種から外れて有料になり、予防接種健康被害救済制度の対象外になってしまいます。
四種混合に不活化ポリオワクチンが加わった令和6年4月に始まった五種混合ワクチンを、国の推奨スケジュールよりも免疫が長持ちする不活化ポリオワクチンの世界の標準接種スケジュールに則って接種することを推奨しています。1回目と2回目の間は1カ月から2カ月、2回目と3回目の間は半年以上あけて、3回目から3年以上あけて4~6才で4回目を接種するスケジュールです。これで最もシンプルに、規定の4回の接種回数で強い免疫を長く得ることができます。
子どもの体調や受け忘れなどの理由で推奨スケジュール通りに接種できないことなどは、よくあることです。規定の接種回数を済ませることが大切で、規定の回数の範囲内なら定期接種として認められますので問題ありません。
同時接種について
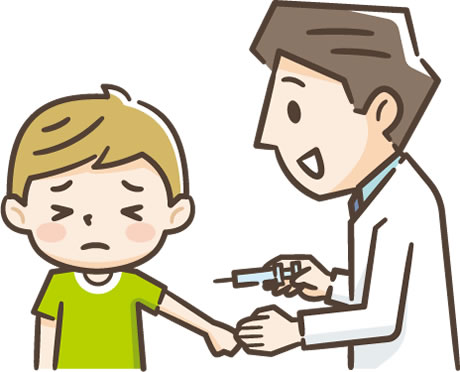
ワクチンは、海外では受けられる年齢に達したら受けるべきワクチンを同時に接種するのが一般的です。
同時に受けたから、副作用が増えることもなければ、ワクチン効果が落ちることもありません。
ワクチンを別々に接種するとなると、毎週のように注射をしなければならなくなるので、その間に他の病気にかかってしまって、接種する時期を逃してしまいますし、他の病気の紛れこみで発熱も多くなって副作用の懸念も増します。
接種のために時間を割かなければならなくなるので、親の負担も大きくなります。
注射を受ける子どもの側からすれば、同時接種だと確かに注射の回数分その場で泣きはしますが記憶の中では1回痛い目に遭ったとしか覚えていないものです。
毎週注射だと、今日も痛い目に遭い、来週も痛い目に遭うと記憶して、病院嫌い医者嫌いになります。
厚生労働省の公式見解として、医師が必要と認めれば、同時接種していいことになっています。
医師が必要と認めればという文言が消極的ですが、早く受けないと病気にかかるリスクを犯すことになるので、私の見解では、接種時期を過ぎれば、少しでも遅らせてはいけないので、いつでも同時接種が必要だと認めます。
これによって生じる健康被害についても、同時接種だから認められないということはないので、ご安心ください。
大半の任意接種のワクチンは定期接種が終わってから接種を始めるのでは遅いので、定期接種とからめて、できるものなら定期接種と同時に受けられるのがお勧めです。定期接種には予防接種健康被害救済制度という国が補償してくれる保険が付いているのですが、任意接種には医薬品医療機器総合機構法に基づく救済といういわば民間保険しか付いてません。万が一ワクチンによる健康被害が生じたときに、定期接種なら接種後の健康被害というだけで高額の補償金と障害が残った場合には生涯にわたって年金が支払われますが、任意接種だと厳しい審査を通って保険が払われたとしても払われる保険金は少額で年金はありません。定期接種と任意接種の同時接種された後に健康被害が生じた場合にも予防接種健康被害救済制度が適用されることになっています。
生後2カ月から生後10カ月までの間に、
・BCGを1回、
・五種混合とヒブと肺炎球菌をそれぞれ3回、
・B型肝炎とロタウイルスを3回
受けることを同時接種でなく一回一回1つずつ接種するとなると、合計16回になり、BCGとポリオの後は次のワクチンまで4週間空けなければいけないので、限りなく困難で不可能に近いです。
これを同時接種にすれば、最少では4回の来院で済ますことも可能です。
ロタウイルスワクチンも受けるとなると、生後2カ月から生後6か月までの間の接種スケジュールがますます過密になります。
現状を鑑みて先を見越せば、同時接種しか道はないのです。
ワクチンの種類
定期接種(11種類)【無料】
- 1)結核へのBCG
- 2)ジフテリア・百日咳・破傷風・ポリオへの五種混合(DPT・IPV・Hib)ワクチン
- 3)麻疹・風疹へのMRワクチン
- 4)日本脳炎への日本脳炎ワクチン
- 5)肺炎球菌ワクチン
- 6)子宮頚がんワクチン
- 7)水ぼうそう
- 8)B型肝炎
- 9) ロタウイルスワクチン
- 10) ジフテリア・百日咳・破傷風・ポリオ・Hibへの五種混合(DPT・IPV・Hib)ワクチン
任意接種(7種類)【有料】
- 1)おたふくかぜ
- 2)インフルエンザ
- 3)A型肝炎
- 4)狂犬病
- 5)帯状疱疹(水痘)
- 6)帯状疱疹(シングリックス)
- 7)狂犬病
ワクチンの料金
予防接種料金は消費税込みです。
| ロタウイルスワクチン※ | ロタテック:7,500円 ロタリックス:12,500円 |
|---|---|
| おたふくかぜ(流行性耳下腺炎) | 4,000円 |
| 水痘(水ぼうそう)※ | 5,000円 |
| 帯状疱疹(水痘) | 5,000円 |
| 帯状疱疹(シングリックス)○ | 22,000円 |
| インフルエンザ | 生後6カ月~3歳未満:3,000円 3歳以上:3,000円 岸和田市在住の65歳以上:1,000円 |
| A型肝炎○ | 6,500円 |
| B型肝炎※ | 10歳未満:4,100円 10歳以上:4,300円 |
| 狂犬病○ | 15,000円 |
| 髄膜炎菌○ | 24,000円 |
| Hibワクチン※ | 8,600円 |
| 肺炎球菌ワクチン(乳幼児用)※ | 9,500円 |
| 肺炎球菌ワクチン(成人用)※○ | 7,600円 |
| 子宮頚がんワクチン※ | 29,771円 |
| 麻疹(はしか)・風疹混合ワクチン※ | 7,000円 |
| 麻疹(はしか)※○ | 4,100円 |
| 風疹※○ | 4,100円 |
| 三種混合(ジフテリア、百日咳、破傷風)※○ | 3,200円 |
| 二種混合(ジフテリア、破傷風)※ | 2,900円 |
| BCG※ | 9,000円 |
| 日本脳炎※ | 5,000円 |
| 不活化ポリオ※ | 7,600円 |
| 五種混合(ジフテリア、百日咳、破傷風、不活化ポリオ)※ | 7,800円 |
| 新型コロナ※ | 12歳以上:15,500円 岸和田市在住の65歳以上並びに基礎疾患を有する60歳以上65歳未満:8,000円 |
※当院は岸和田市から予防接種の委託を受けていますので、委託分(※がついている予防接種)は無料です。
○常時は在庫がないので事前に電話で連絡しておいてください。
予防接種料金は消費税込みです。
小児のインフルエンザワクチンの接種回数
小児のインフルエンザワクチンの接種回数が医師によって違っていて、毎回2回必要と言われたり、1回で良いと言われたりします。どちらが正しいのでしょうか。
実は、医師がワクチン接種回数を決める根拠が違うからこうなるのです。
ワクチンの添付文書に書かれていることは、用法・容量は6ヶ月から13歳未満までは2回接種ですから、添付文書に従えば13歳未満は全員2回接種が正しいです。
でも同じ添付文書にある臨床試験の結果では、3歳未満では1回目後と2回目後の抗体価は約2倍に上昇しますが、3歳以上では1回目後と2回目後の抗体価はほぼ同じか微かな上昇です。ワクチンも医薬品の1種なので、臨床試験の結果を重視するなら、3歳以上は1回接種で十分ということになります。
保険診療なら添付文書通りに処方しないと違反行為になりますが、インフルエンザワクチンは任意接種なので、医師の判断で診療方針を決められます。接種回数を減らしたことで副作用や有害事象が増えることはありません。
WHOは過去3年以内に複数回接種していれば1回接種を勧めています。9歳以上は原則1回接種です。この勧告は世界中で実施されたインフルエンザワクチンの研究のデータから総合的に導かれたもので、国際標準であり、世界的に一番説得力があります。
あぶみ小児科クリニックでは、国際標準に準拠した以下の接種回数をお勧めします。
小児で初めての人は必ず4週間隔で2回接種。
過去3年以内に複数回受けている人は1回接種で、そうでない人は2回接種。
3歳未満で希望されれば上乗せ効果が期待できるので、2回接種しても良い。
9歳以上なら過去に接種歴があれば1回接種。
乳幼児炎の重症の胃腸炎を防ぐ「ロタウイルスワクチン」
現在の日本で、ワクチンで防げる病気の中で、とても伝染力が強く子どもが実際にかかって、救急外来を受診したり入院したりする病気
ロタウイルス胃腸炎とは
白っぽい水のような下痢や激しい嘔吐が続き症状が治まるまでに7日間程度かかります。赤ちゃんは水分補給が間に合わなくなり、口から何も受け付けなくなったりして、急激に脱水が進んで、すぐに適切な処置をしないと命にかかわることもあります。
発展途上国を含めた全世界の乳幼児死亡では死因の最上位を占める病気です。日本でも外来受診した子どもの15人に1人は入院しています。日本でロタウイルス胃腸炎で入院する小児の3割が0歳児、4割が1歳児です。
ロタウイルスワクチンでロタウイルス腸炎にかかりにくくなり、重症化を防ぎます。ロタウイルスワクチンはポリオワクチンと同じように口から飲むワクチンで、生後6週から6カ月までの間に4週間以上あけて2回または3回接種します。
ワクチンでしか防げない病気です。
乳児や低年齢児がかかる病気で、5歳までに必ずかかる病気です。流行し始めたから急いでワクチンを受けようと思っても、既に子どもは生後5カ月を過ぎていて受けることができません。定期接種ではなく親の判断で受ける任意接種ですから、子どものために先手を打てる親の理解力が問われるワクチンです。
子宮頚がんを防ぐワクチン
若い女性がかかる癌で、ヒトパピローマウイルスの持続感染が発癌を起こす子宮頚がんは、発癌性のある型のウイルスに感染しなければ予防できます。
このために開発されたのが「子宮頚がんワクチン」です。
ヒトパピローマウイルスは、人の皮膚や粘膜に普通に潜むありふれたウイルスなので、セックスをすれば簡単にかかります。処女のうちに済ますべきワクチンです。
ワクチンを受けて一次予防して、成人後は子宮癌検診を欠かさなければ防げる病気です。
ワクチン後に接種部位に痛みを感じる人が大半ですが、1週間以内に97%は消失します。
痛みが持続する段階で早めに鎮痛剤で痛みを除去すれば遷延を防げます。
3回接種完了しなくても2回接種でも有効性が確認されています。
WHO(世界保健機構)のワクチン諮問委員会は27年12月23日に積極的勧奨を中止している日本を「若い女性をヒトパピローマウイルスによるがんの危険にさらしている」と批判する声明を出しました。「薄弱な根拠によって有効なワクチンを使わないことは、実質的な損害につながる」と警告しています。
日本では中止に近い状態なので研究できない状態ですが、フランスで200万人の少女を対象とした研究では、接種者と未接種者との間で症状の発生にほとんど差がありませんでした。
名古屋市の1994年度から2000年度生まれの7万人の少女を対象にした研究(名古屋スタディ)では、接種者と未接種者の間でワクチンで生じるとされる症状の発生に差がなく、接種者は接種したからか症状を心配して受診される割合が多いという結果でした。
あぶみ小児科クリニックでは積極的に接種を勧めています。
おたふくかぜについて
おたふくかぜは、「任意接種」と呼ばれて、「受けたい人だけが受ければ良いワクチン」と誤解されています。
ワクチンがある病気とは、決して罹った方が良いなどということは言えない重要な病気なのです。
「ワクチンで予防するよりも実際に病気にかかる方が強い免役が得られるから、ワクチンは要らないのでは」と、言われる方にたまにお目にかかりますが、間違いです。
MR(麻疹風疹混合)は、日本だけで、海外ではMMR(麻疹おたふくかぜ風疹混合)です。
先進国で国民全員におたふくかぜワクチンを接種していないのは日本だけです。おたふくかぜに自然感染すると千に1の確率で耳が聞こえなくなります。感音性難聴といいますが、治癒することはありません。これがおたふくかぜワクチンが必要な最大の理由です。
ワクチンの副作用について
日本ではワクチンと言うと、効果よりも副作用ばかりが喧伝される傾向が強いですが、病気にかかると失われる健康と副作用を比較して、ワクチンを受ける方の利益が大きいワクチンだけが実際には使用されています。
ワクチンを接種して発熱がみられることは、そもそも免疫をつけるということが必ずと言って良いほど発熱を伴うものなので、副作用に含まれるものではありますが、元気で発熱するだけなら受け入れるべきものです。
私などは、仕事柄毎年インフルエンザワクチンを受けるのですが、たいてい受けた後は熱っぽくなってだるくなります。
「ヒブワクチン」・「肺炎球菌ワクチン」・「子宮頚がんワクチン」の特徴
〇一度では効果が弱く、何回も注射を受けなければならない
〇注射部位が発赤腫脹しやすく、発熱を伴いやすい
「肺炎球菌ワクチン」の後の発熱と、接種部位の発赤腫脹、「子宮頚がんワクチン」の後の接種部位の発赤腫脹は、従来のワクチンと比べると目立ちます。
接種部位にワクチンの注射液が留まって局所反応を起こしての接種部位の発赤腫脹や発熱なので、局所を氷枕やアイスノンなどで赤くなくなるまで十分に冷やすことが局所反応と発熱を抑える方法になります。冷えピタでは効きません。しっかりクーリングしてあげてください。